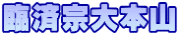 |
|
臨済宗と鎌倉五山
|
日本における禅宗は、鎌倉時代初期、明庵栄西により伝えられた臨済禅を起源とする。現在はその臨済宗に加え道元禅師を開祖とする曹洞宗と中国の明僧隠元禅師の開山による黄檗宗の三宗派がある。
臨済宗の大本山は、鎌倉には建長寺と円覚寺。京都には妙心寺、南禅寺、建仁寺、東福寺、天龍寺、相国寺、大徳寺がある。また宇治市には黄檗宗の大本山萬福寺がある。
五山とは、禅宗で最高の格づけをされた五大寺をいう。鎌倉時代に中国の五山制度にならって、最初鎌倉の禅寺に設けられた。建武の中興から京都にも五山に列せられるものがでて、さらに室町初期には鎌倉・京都それぞれに設置された。その後たびたび改定されたが、1386年(至徳3年・元中3年)足利義満のとき、五山の上に南禅寺がおかれ、京五山として天竜寺・相国寺・建仁寺・東福寺・万寿寺。鎌倉五山として第一位建長寺・第二位円覚寺・第三位寿福寺・第四位浄智寺・第五位浄妙寺の順と定められ、現在に至っている。
|
鎌倉は町中に12世紀から続く古都の雰囲気が残っている。なかでも散在する寺々は鎌倉の歴史をそのまま伝えるものとしてきわめて興味深い。今回訪れた寺のなかでも時代の移り変わりによって衰退し、かつての隆盛の面影なく、ひなびた寺になっているところもあった。しかし、それがかえっていい味になっていた。広大な寺域に多くの伽藍が並ぶ大寺院もいいが、ひっそり建つ由緒ある小さいお寺はもっといい。
(2003年10月) |
|
|
| 鎌倉五山と周辺の古刹を巡る |
|
|
|
| 建長寺 |
巨福山(こふくざん)建長興国禅寺は、鎌倉五山第一位の臨済宗・建長寺派の大本山である。北条時頼が、建長五年(1253)に宗から来日していた高僧・蘭渓道隆を招いて建立したわが国最初の禅寺である。
|
| 三解脱門(三門) 安永4年(1775)の再建 |

|
|
| 三門扁額 建長興国禅寺 |
 |
|
|
銅板葺き屋根入母屋造り、高さ約30メートル。
安永4年(1775) に再建した重層門で、楼上には五百羅漢像が祀られている。 |
 |
|
|
| 仏殿 |
| 芝・増上寺の廟所が移築されたもの |
 |
|
| 建長寺 本尊 地蔵菩薩 |
| 仏殿に祀られている。如来ではなく、菩薩を本尊にしているのが意外な感じがする。 |
 |
|
|
| 円覚寺 |
鎌倉五山第二位の円覚寺は、鎌倉幕府八代執権・北条時宗が弘安五年(1282)に創建した臨済宗・円覚寺派総本山である。文永・弘安の役で蒙古の大軍を撃破した時宗は、両軍戦死者の菩提を弔い、己の精神的支柱となった禅宗を広めたいと願い、その師・無学祖元(仏光国師)への報恩の念から、祖元を開祖に円覚寺を建立した。
|
|
総門
 |
「瑞鹿山円覚興聖禅寺」が正式山号寺号

|
|
山門
|
 |
仏殿(大光明寶殿) |
 |
|
 |
洪鐘(梵鐘)
北条貞時寄進によるもので国宝に指定されている |
|
 |
|
|
|
| 寿福寺 |
| 寿福金剛禅寺は臨済宗建長寺派の寺で、鎌倉五山の第三位である。源頼朝の父・義朝の居館があった所でもある。頼朝が建久10年(1199)に亡くなると妻・
f北条政子が夫の菩提を弔うため、正治二年(1200)に明庵栄西を招いて義朝ゆかりの土地に創建した。 |
| 三門 |
 |
|
| 寿福寺三門扁額 |
 |
|
| 本堂 本尊宝冠釈迦如来を祀る
|
 |
|
|
|
| 浄智寺 |
臨済宗円覚寺派・淨智寺は、鎌倉五山の第四位である。
鎌倉幕府五代執権・北条時頼の三男・宗政が29歳の若さで弘安四年(1281)に没し、八代執権・北条時宗が弟の菩提を弔う為に、その夫人と子・師時を開基として建てた寺である
|
| 参道 |

| 三門 |

|
|
|
|
|
 |
|
二階部分に鐘をさげた中国風の門。
創建時には中国の職人によって建てられ、後年、当時の絵地図をもとに修復されたために中国様式が残った、とされている。
|
|
 |
|
| 本堂(曇華殿) |
 |

|
|
| 本尊 三世仏座像 |
左から阿弥陀、釈迦、弥勒で過去、現在、未来をあらわす。室町期の作品。仏殿に安置される。
|
 |
|
|
|
| 浄妙寺 |
稲荷山淨妙禅寺は臨済宗建長寺派の古刹。鎌倉五山の第五位で文治四年(1188)に、源頼朝の忠臣で豪勇であった足利義兼が開創し,始めは極楽寺と称した。開山は退耕行勇と伝えられる。
|
| 総門 |
 |
|
| 本堂 |
 |
|
|
|
| 東慶寺 |
松岡山・東慶寺は臨済宗・円覚寺派に属する寺。開山は北条時宗夫人・覚山尼。北条時宗の菩提を弔う為にその子・貞時を開基として、弘安八年(1285)開創。第5世用堂尼(後醍醐天皇の皇女)の入寺以後、松ヶ岡御所と称され、寺格の高い尼寺としてその名を馳せるようになった。明冶に至るまで男子禁制の尼寺で駆け込み寺または、縁切り寺として、あまたの女人を救済した。縁切り法を成立させたのが寺を開いた覚山尼と言われる。
|
山門 |
 |
|
| 本堂 |
 |
|
|
|
|
| 明月院 |
臨済宗建長寺派 福源山明月院は当初「明月庵」として永暦元年(1160)に創建された。
その後、康元元年(1256)北条時頼がこの地に「最明寺」を建立し、のちに北条時宗が最明寺を前身として「福源山禅興仰聖禅寺」を再興した。
康暦二年(1380)以降に伽藍を整備して寺域を拡大し、支院を配置した。明月庵は「明月院」と改称して支院の首位におかれたが、明治初年に興禅寺が廃寺となり、「明月院」のみを残して今日にいたる。
(明月院パンフレットから)
|
| 山門 |

|
| 山門前の両側にはあじさいが植えられていて、開花時期には見事な景観を呈し大勢の人が押し寄せる。すり減った階段がその人気を物語る。 |
「福源山」の扁額
 |
|
宗猷堂(そうゆうどう)
開山である密室守厳(みっしつしゅげん)像を置いてある |
 |
|
|
| 方丈(本堂) |
 |
|
|
| 方丈の茶室から後庭園を臨む円窓 |
 |
|
|
| 方丈の前庭 枯山水庭園 |
 |
|
|
|
| 報国寺 |
報国寺は臨済宗建長寺派の禅宗寺院。この寺は、淨妙寺中興の足利貞氏の父・家時(足利尊氏の祖父)が開基。夢想国師の兄弟子・天岸慧広(仏乗禅師)の開山で建武元年(1334)に創建された。
|
|
| 山門 |
 |
|
|
| 本堂 |
 |
|
|
| 梵鐘 |
 |
|
| 枯山水 |
 |
|
孟宗竹の竹林
|
 |
|
|
| 各寺院の説明文は(「鎌倉ぶらぶら」http://www.kamakura-burabura.com/meisyokitakamakuratoukeiji.htm)等を参考にしております。 |
|
|
|



































