 |
一山の総門
山岳宗教の結界の象徴
宝永2年(1705)の再建という。 |
|
|
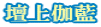 |
| 壇上伽藍は、高野山開創のときに空海が堂宇を造った地で高野山真言密教の中核となる場所である。現在ここには金堂、御影堂、根本大塔、不動堂など15の堂や塔が建ち並んでいるが、その多くは江戸時代から昭和時代の再建である。そのうち鎌倉時代の不動堂は国宝となっている。 |
|
|
 |
根本大塔
高さ48.5mの高野山を代表する建造物。内陣には胎蔵界大日如来を本尊として金剛界四仏(阿閦(あしゅく)、宝生(ほうしょう)、阿弥陀、釈迦)がともに安置されるという異例の配置となっているが、根本的には両者はひとつという空海の思想を反映したものという。
この大塔は建立以来落雷などでたびたび焼失・再建をくりかえし、現在の建物は鉄筋コンクリート建てで1937年(昭和12年)に完成した。外装は木造仕上げになっているという。 |
|
|
 |
金堂
空海が壇上伽藍のうちでもっとも早く建てたものだが、やはり焼失・再建を繰り返し、現在の金堂は6度目の再建で、1932年(昭和7年)に竣工した。鉄筋コンクリート構造で、木造仕上げとなっている。
本尊の薬師如来(秘仏)は昭和元年の火災で焼失してしまい、現在は高村光雲作の薬師如来像が安置されているが秘仏として非公開である。
|
|
|
|
 |
不動堂
鎌倉時代の建物で国宝。
本尊の不動明王座像は平安時代の作で重要文化財指定されているが、現在は近くの霊宝館に収蔵されているという。 |
|
|
|
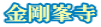 |

|
 |
金剛峯寺主殿
高野山真言宗総本山で、全国3600におよぶ末寺の宗務を執り行う。
もともと金剛峯寺の名は高野山一山の総称であったが、豊臣秀吉の建てた青厳寺が明治初年に金剛峯寺と改められた。
|
|
|
|
 |

奥の院正門
奥の院御廟は約1km先にある。右の石柱に書かれた「南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)」は弘法大師への崇敬を唱えることば。 |
|
 |
奥の院は20万基を超える墓や供養塔が並び、世界最大の墓地と言われる。
これは、弘法大師の足元に眠ることによって極楽往生できるという信仰による。このため古来より戦国武将などの歴史上の人物がこの地に名を連ねているが、これは一般大衆も同じで全国各地からここに墓を求める人々が今でも絶えないという。 |
|
|